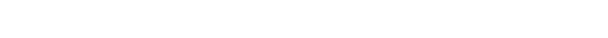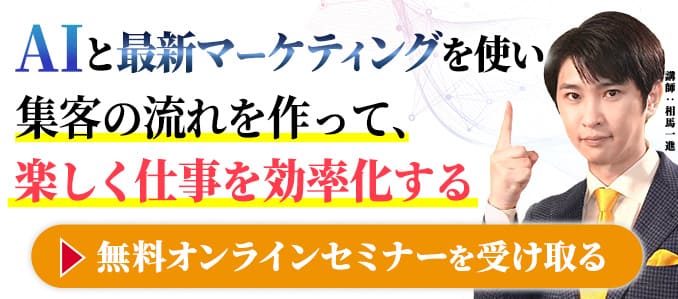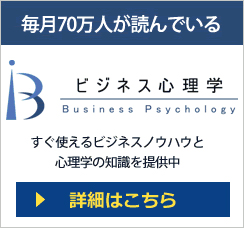こんにちは。
相馬一進(そうまかずゆき)です。
今回からの記事は、
「人との距離感がわからない、愛着障害」をテーマに
シリーズ形式でお伝えします。
あなたは愛着障害って知っていますか?
簡単に言えば、子どものときに親との間に
「安定した愛着関係」を築けなかったことで、
人間関係がハードモードになる障害のことです。
ハードモードとは、たとえば次のような傾向です。
・必要以上に人を避けてしまって孤立する
・「誰かに見捨てられるのではないか」と、
常に不安を感じる
・自己肯定感が低いなど感情が不安定になりやすい
あなたやあなたの周りの人には、
こういった傾向はありませんか?
もしあるなら、今回のシリーズは必読です。
なぜなら、愛着障害の原因や特徴、克服法について
解説するからです。
まず、「愛着」の正しい意味を説明しましょう。
愛着とは心理学用語なのですが、
「心理的な安心感」のことです。
たとえば、3歳くらいの子供が転んでしまって
泣いたときに、親が「よしよし」と
優しく抱っこしてくれるじゃないですか。
このときに子供が感じる「安心感」のことを
愛着と言います。
では、この愛着が弱いとどうなるかわかりますか?
答えは、子供の頃はもちろん、大人になっても
人生がうまくいかないことが科学的にわかっています。
孤独感や空虚感ばかりの人生になりがちなんですね。
「三つ子の魂百まで」という感じです。
つまり、人生の質は「幼少期の育てられ方」によって
大部分が決まるんです。
さて、私は、起業家を中心にのべ1,000人以上に
心理学を教える講座をやってきました。
このような講座をやることになった理由は、
私も典型的な愛着障害だったからです。
メンタルがクソ弱くて、
人生をかけて心理学を勉強したら、
心理学を教えることが仕事になっていました。
愛着障害に関しては、
横浜国立大学で心理学を教えていた
堀之内貴久先生から私は多くを学びました。
ですので、この愛着障害については熟知しています。
「誰かと一緒にいても、心の中ではずっと寂しい」
と悩んでいた私のクライアントも、
人間関係をうまく築けるようになりました。
また、「自分には価値がない」と考えていた
自己肯定感が低いクライアントも、
「ありのままでよい」と思えるようになっています。
ですので、もしあなたやあなたの周りの人に
愛着障害の傾向があるなら、
ぜひ読んでみてください。
=======================
『 人との距離感がわからない、愛着障害(第1回目)』
幼少の愛着障害で人生が詰む話
=======================
では、愛着障害について、
もう少し詳しく見ていきましょう。
愛着障害は、医学的な概念ではあるのですが、
病名ではありません。
ただし、不安障害やうつ病や
境界性パーソナリティ障害といった
精神疾患の原因とされています。
愛着障害とは、性格というよりも、
「発達上のトラウマ」に近いんです。
ここで、あなたに質問です。
愛着障害でどれくらいの人が悩んでいるか
イメージがつきますか?
かなりの数の論文を調べても
載っていませんでしたが、日本人のうち、
ざっくり5〜10%くらいじゃないかと推定されます。
一応、その根拠をお伝えしますね。
大阪大学の研究によれば、
「約60%の被験者が不安定型の愛着スタイルだった」
とわかっています。
ざっくり言えば、日本人のうち、
人間関係が不安定になりやすいのは60%という意味です。
意外と多いでしょ?
大学生の愛着スタイルと自己意識および
他者意識との関連性
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpnjschhealth/61/6/61_331/_pdf
その60%の中で、
精神科で治療を受けなければいけないほど重篤なのは、
人口比で数%と言われています。
なので、それよりももうちょっと多いくらい、
おそらく5〜10%の人が愛着障害という推定です。
それくらいの割合の人が
「精神科で治療を受けるほどではない。けれども、
社会生活を送るのが結構きつい」と悩んでいるはずです。
なので、ここで扱っている愛着障害も、
このレベルを指しています。
愛着障害について、ざっと理解できましたか?
次に、愛着について、
非常に重要なクイズです。
愛着と愛情は何が違うのでしょうか?
パッと見は似ていますが、意味はまったく違います。
まず、愛情とは、
誰かに対する親密な感情のことです。
脳内ではドーパミンやノルアドレナリンが分泌されて、
「好き」とか「ドキドキ」という感情を作り出します。
たとえるなら、打ち上げ花火のように
ドーンと上がって秒で消える瞬間的な快楽ですね。
イメージしやすいでしょ?
一方、愛着とは安心や安全の感情のことです。
脳内ではオキシトシンとバソプレシンが分泌されて、
「ほっとする」とか「安心する」と感じます。
たとえるなら、
ひだまりのようなずーーっと続く安心感です。
この「ひだまりのような安心感」という意味、
あなたはわかりますか?
愛着障害の人は、
この意味がわからないことが多いです。
実は私もわかりませんでした。
だって、私って愛着障害のサラブレッドなんですよ。
私の父も愛着障害、私の母も愛着障害、
そして私も愛着障害だからです。
「じゃあ、どうやって相馬さんは
ひだまりのような安心感を知ったんですか?」
と思うかもしれません。
あるとき、心理学の本を読んだんです。
そうしたら、「まるでひだまりのような
安心感があるのが、健全な人間関係の特徴です」
と書いてあったんですね。
「えええーー、どういうこと?」
と驚いたんですね。
だって、意味が理解できなかったからです。
当時の私が築いていた人間関係って、
良く言えばドキドキがあるもの、
悪く言えば恐怖感があるような関係だったんです。
たとえば、「嫌われるのが怖い」とか
「自分の本音を怖くて話せない」と感じていました。
なので、「ひだまりのような安心感がある
人間関係なんて存在するんだ!」と驚いたんです。
そんな感覚を、
それまで私は感じたことがなかったからです。
あなたは、
「健全な人間関係ではひだまりのような安心感がある」
と言われて信じられますか?
もしあなたが私と同じように愛着障害であれば、
信じられないのではないでしょうか。
「UFOは存在する」みたいに言われた感じです。
とにかく、
「健全な人間関係は、ひだまりのような安心がある」
と覚えておいてくださいね。
これ、テストに出ますよ(笑)
それにしても、
なぜ幼少期に愛着を築くことが重要なのでしょうか?
そして、幼少期に愛着を築かないと、
なぜ大人になっても孤独感や空虚感ばかりの人生を
送ることになるのでしょうか?
それは、愛着が単に心を安定させるだけでなく、
生物としての生存と深く結びついているからです。
ポケモンで言ったらキズぐすりですw
ないと詰むやつです。
あなたは、動物心理学者のハリー・ハーロウが
1950〜1960年代に行ったアカゲザルの実験を
知っていますか?
これ、マジで興味深い実験なんですよ。
実験では、生まれたばかりのアカゲザルの赤ちゃんが、
2種類の「代理の母」と共に置かれました。
1つはミルクが出る哺乳瓶がついた、
針金でできた「母」です。
もう1つはミルクは出ないけれど、
布で覆われた「母」です。
ミルクの代わりにヒーターがついていて、
肌のぬくもりを感じることができました。
それで、サルはどちらの代理の母を選んだと思いますか?
サルたちは、お腹が空いたときに
針金の母の元に行き、哺乳瓶からミルクを飲みました。
しかし、それ以外の「ほとんどの時間」は、
布で覆われた温かい母にしがみついて過ごしたのです。
意味、わかりますか?
サルにとっては、ミルクという生存に必要な要素は
あまり重要ではなかったのです。
「えっ、マジで?」って驚きますよね?
ミルクよりも、
「温かさ」や「肌の触れ合い」から得られる
安心感の方が大切だったんです。
この実験は、愛着という心理的な安心感が
生存に不可欠であることを証明しました。
「サルの実験はわかった。でも、これって
人間にも当てはまるの?」と思いませんか?
思うでしょ?
ということで説明します(笑)
これからお伝えするのは1980〜1990年代の、
ルーマニアの孤児院での事例です。
当時、ルーマニアでは、
人口増加政策により多くの孤児が生まれました。
当時のルーマニアの独裁者は、
「人口を増やしたい。だから中絶も避妊も禁止!」
と言ったんです!
「ええっ、マジかよ!」と思いませんか?
これ、やばいでしょ?
政策っていうより、ただのゴリ押しじゃないですか!
その政策の結果、
たしかに赤ちゃんは爆発的に産まれました。
でも、同時に孤児院に預けられる赤ちゃんも
爆発的に増えてしまいました。
「うちでは育てきれない」という親が、
口減らしをしたからです。
そりゃー、そうでしょ!
孤児になった赤ちゃんが可愛そうですよね。
そして、興味深いのはここからです。
孤児院では、十分な食事は与えられていました。
しかし、スタッフの数が不足していて、
抱っこなどのスキンシップがほとんどありませんでした。
その結果、何が起こったと思いますか?
孤児院で育った子どもたちは、
死亡率が著しく高かったのです。
さらに、生き残ったとしても、
体と心の発達が遅れたのです。
怖くないですか?
ゾッとしますよね?
これは、アカゲザルの実験結果と同じ現象です。
子供に食事を与えても、愛着が足りないと、
生存そのものに影響を及ぼすのです。
この論文のリンクを貼っておくので、
興味があれば読んでみてください。
Emotion, Space and Society
https://philarchive.org/archive/SIMIAT
ちなみに、この論文には
他にも衝撃的なデータがいくつも載っています。
たとえば、1915年のアメリカの孤児院では、
「ほぼ全て」の赤ちゃんが2歳までに死亡していました。
これも、恐ろしくないですか?
北朝鮮の孤児院だって、もっと死亡率低そうですよねw
それにしても、
なぜほぼ全ての乳児が死亡したのでしょうか。
ミルクをあげられていなかったから?
違います。
愛着がほとんどなかったからです。
当時の孤児院の方針は、
「清潔第一」でした。
なので、病気にならないように乳児を隔離し、
人との接触を極力避けていたんです。
その結果、乳児は栄養は与えられても、
抱っこなどのスキンシップや優しい声かけなどの
人間的な関わりをほとんど持てなかったのです。
これが、ほぼ全ての赤ちゃんが死亡した原因でした。
「愛着は生存に必要」という意味、わかりましたか?
インテリぶって説明するなら、
聖書の表現で「人はパンのみにて生くるにあらず」
という言葉があるじゃないですか。
要は、「食べ物だけじゃなくて、精神的なものも
人間が生きる上で大切だよ」という意味ですね。
「それな!」って感じですよね。
さて、この愛着を感じるセンサーは
主に幼少期に作られることをご存知でしょうか?
まず、前述したとおり、愛着に特に関係するのは
オキシトシンというホルモンです。
このホルモンは、親とのスキンシップや
優しい声かけによって、子供の脳内で分泌されます。
そして、このホルモンを受け取るセンサーが
オキシトシン受容体です。
あなたは、受容体ってわかりますか?
簡単に言えば、オキシトシンが「鍵」だとすると、
受容体は「鍵穴」のようなものです。
まず、オキシトシンという鍵が、
受容体という鍵穴にぴったりとハマります。
すると、脳や体が「愛着」を感じ取るのです。
このオキシトシン受容体は、幼少期に形成されます。
しかし、ネグレクトや虐待などがあると、
幼少期に十分なオキシトシンが分泌されません。
すると、オキシトシンの受容体も
十分に形成されません。
その結果、大人になっても、
周りからの愛着を感じ取る「センサー」が
存在しない状態になるのです。
愛着はそこにあるのに、受け取ることができない。
悲しいですよね?
だから、幼少期に愛着を築けなかった人が、
大人になっても苦しむのです。
たとえ誰かと一緒にいたとしても、
心の中がずっと孤独感や空虚感でいっぱいだからです。
これが、幼少期に愛着を築くことが重要な理由なんです。
人生の質は「幼少期の育てられ方」によって
大部分が決まる、といった意味、理解できましたか?
「愛着の大切さはよくわかった」
「でも、具体的にどんな育てられ方をしたら
愛着障害になるの?」って思いませんか?
そこで、次回の記事では、
愛着障害の原因を解説します。
=======================
「人との距離感がわからない、愛着障害」の
第1回目は以上です。
次回も、愛着障害を克服するために
とても大切な内容なので、
ぜひ読んでいただければと思います。