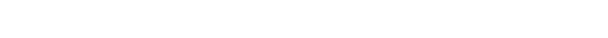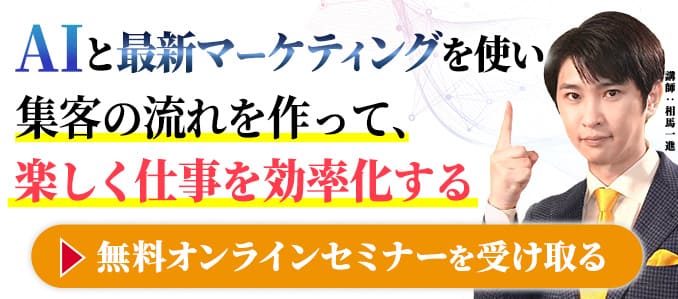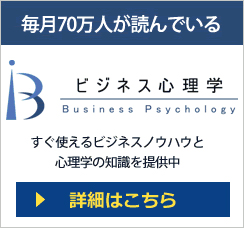こんにちは。
相馬一進(そうまかずゆき)です。
今回は、
「高IQほどハマるマーケティングの落とし穴」の
第4回目、最終回です。
この最終回では、
「ブルー・オーシャン戦略」の落とし穴を
タピオカドリンク専門店を例に解説します。
あなたは、2019年に大ブームを巻き起こした
タピオカドリンク専門店を覚えていますか?
タピオカドリンク店は、
一時は行列ができるほどの人気でした。
しかし、わずか1年でほとんどが姿を消したのです。
これは、「ブルー・オーシャン戦略」の
末路を示す典型例です。
ブルー・オーシャンとは、
「競争が皆無で、大きな利益を出せる市場」
という意味のマーケティング用語です。
「競争のない青い海」というたとえから、
血で染まった赤い海(レッド・オーシャン)と
対比される概念として使われます。
IQの高い多くの経営者たちは、
このブルーオーシャン戦略に魅力を感じています。
しかし、エビデンスに基づいて言うと
競争のない市場など存在しません。
これは、驚くべきことに
ブルーオーシャン戦略の提唱者自身が
認めている事実なのです。
「いったいどういうこと?」と思いませんか?
今回は、その答えを解説するとともに
ブルー・オーシャンを探すよりも圧倒的に成功率の高い
マーケティングの戦略も紹介します。
あなたのビジネスを持続的に成長させるために、
必ず最後まで読んでください。
なお、第1回目から第3回目では
「ターゲティング」「差別化」「ヘビーユーザー重視」
の落とし穴についても解説しました。
まだ読んでいない場合は、ぜひそちらも読んでみてください。
=======================
『高IQほどハマるマーケティングの落とし穴
(第4回目)』
タピオカドリンク屋はなぜ消えた?
=======================
さて、ブルー・オーシャンの理論は、
W・チャン・キム教授らによって
2005年頃に爆発的に広まりました。
そして、理論を学んだIQの高い経営者の多くが、
競争のない市場を探し求めました。
しかし、前述したとおり、
ブルー・オーシャンは存在しません。
その理由は、冒頭でも触れた
タピオカドリンク専門店の例を見れば明らかです。
タピオカドリンクのピークはいつ頃だったと思いますか?
「グーグルトレンド」という
グーグル検索キーワードのトレンドがわかる
ツールのデータを調べると、2019年6月でした。
そして2020年にコロナ禍が追い打ちをかけ、
一気に店舗数が減少していきました。
では、なぜタピオカドリンクのブームは
去ったのでしょうか?
その理由は、株のバブル崩壊と同じ構造なのです。
具体的に解説しましょう。
まず、ごく少数の賢い起業家が
「タピオカドリンク屋は儲かりそうだ」
と考え、ブームが始まる前に出店します。
ブームが始まる前に参入できれば、当然儲かります。
しかし、実はこの瞬間「だけ」が
ブルー・オーシャンだったのです。
私、ブルー・オーシャンだったときの
タピオカドリンク屋をよく覚えているんですよ。
私の家の近所が再開発された2018年頃、
タピオカドリンク屋がテナントとして入っていて
驚いたからです。
「えっ、10年以上前に流行ったあのタピオカ?
今どき売れるの?」と思ったものです。
その後、メディアが報道し始めました。
「最近、タピオカドリンクがまた流行り始めました!
女子高生の間で大人気です!」と。
すると、当然タピオカドリンクの需要が増え、
普通の起業家も参入し始めます。
「タピオカドリンク屋を開店しても、
今ならまだ利益が出るだろう」と考えるからです。
そしてバブルの最終段階では、
どのメディアもタピオカドリンクを
爆発的に取り上げていました。
その結果、私の家の近くのタピオカドリンク店には
行列ができていました。
しかし、メディアは何度も同じものを
取り上げ続けることはありません。
メディアが一通り取り上げたら、
ブームが去りお客さんは減ります。
当然ですよね?
だいたい、こういうブームって女子高生から始まって
中高年にまで広まると終わるんです(笑)。
ところが、このブームの終盤のタイミングで
頭の悪い起業家が山ほど参入するわけです。
「これだけ流行っているなら、
じゃんじゃん利益を出せるだろう!」と
強欲になっているからです。
やばいでしょ?
その結果、供給過剰になって利益が出なくなるんです。
タピオカドリンク屋には、
確かに2018年頃に一瞬だけ
ブルー・オーシャンだった時期がありました。
当時はタピオカドリンク店がほとんどなく、
先行者利益を得られる状態でした。
しかし、ブームが始まると、
すぐに猿真似をする起業家が参入してきて、
ブルー・オーシャンはすぐに消滅してしまったのです。
「相馬さんは、何を当たり前のことを
言ってるんだ」と思われるかもしれません。
ですが、ここに落とし穴があります。
平均以上のIQを持つ人は、
「ブルー・オーシャンは存在するものだ」
と思っている場合が多いのです。
もっと言うと、
「ブルー・オーシャンを見つければ、安泰だ」
と思っている場合さえあります。
これこそが落とし穴です。
繰り返しますが、
ブルー・オーシャンなんて存在しません。
仮に存在したとしても、すぐに参入されて
一瞬でレッドオーシャンに変わってしまいます。
つまり、ブルー・オーシャン戦略とは
新しい市場を開拓するための
戦略でしかないということです。
言い換えれば、無競争を作り出す戦略でもなければ、
参入障壁を作る戦略でもないということです。
ここを勘違いしないでください。
ブルー・オーシャンとは、
綺麗だけど、すぐに消えてしまう
シャボン玉のようなものです。
したがって、ブルー・オーシャンが続くと信じるのは
シャボン玉がずっと割れないと信じるのと
同じくらいバカげているんです。
ここまでの話を聞いて、
あなたはこう思いませんか?
「ブルー・オーシャンが存在しないことは
わかったけれど、どうすればいいの?」と。
答えを一言でいえば、
「新しい市場を開拓すること」です。
『ブルー・オーシャン戦略』という
本の中にも多くの事例が紹介されています。
その中から、日本人にも馴染みが深い
任天堂のWiiの事例をご紹介しましょう。
任天堂のWiiの開発スタッフは、
『ブルー・オーシャン戦略』の本を読み込み、
Wiiを作ったそうです。
その際、子供だけではなく、
いろいろな世代に売れるゲームを作ろうとしました。
昔は、「ゲームは子供のためのもの」
という考え方が一般的でした。
そこで、新しい市場として
普段はゲームをしないような大人でも遊べる
ゲームを作ったのです。
たとえば、ヨガなどができる『Wii Fit』や
ゴルフなどができる『Wii Sports』などの
大人向けのゲームですね。
ここがポイントです。
「新しい市場を開拓する」とは、別の言い方をすると
「ノンユーザーを獲得する」ということです。
ノンユーザーとは、そのカテゴリーの商品を
全く買わない人のことです。
このノンユーザーにも売れるような、
商品を作ることが重要なのです。
結局のところ、
ブルー・オーシャンを見つけたとしても
それはすぐにマネされてしまいます。
なので、「市場の中で競争があるか、ないか」には
フォーカスしない方がいいのです。
では、どうすればいいかというと、
「常に新市場を開拓すること」にフォーカスするのです。
ビジネスがどんなに大きくなったとしても、
自分の商品をまだ買ってくれていないお客さんは
たくさんいるわけです。
ですから、そういったノンユーザーに
買ってもらうことを考えてほしいのです。
「でも、その方法って自分のような中小企業や
個人事業主でもできる方法なの?」
と思うかもしれませんね。
そこで、私の事例をご紹介しましょう。
ノンユーザーに買ってもらうことを、
私はずっと意識してきました。
たとえば、私は起業家向けに
販売や集客の方法を教える講座を開催していました。
そして、その講座を起業家ではない人にも
買ってもらおうと思いました。
具体的には、起業準備中で副業などをしている
会社員にも販売したのです。
その結果、私は起業準備中の人にも
価値を届けることができました。
この動画で話しているような
本質的なマーケティングの内容であれば、
起業家でなくても役立ちますよね?
そして、その講座は毎年1億円以上の売上を
弊社にもたらし続けてくれるようになりました。
ノンユーザーを獲得することで、
このような結果が得られるのです。
ですから、新市場を開拓するほうが
ブルー・オーシャンよりもはるかに重要なのです。
今回は、ブルー・オーシャン戦略の
落とし穴を解説しました。
ここまで読んでくれたあなたは、
ぜひちまたのマーケティングの常識を鵜呑みにせず
エビデンスのあるマーケティングを実践してください。
=======================
「高IQほどハマるマーケティングの落とし穴」
のシリーズは、これで終わりです。
今後も、エビデンスに基づいて
あなたのビジネスに役立つ情報をお伝えするので
楽しみにしていてください。